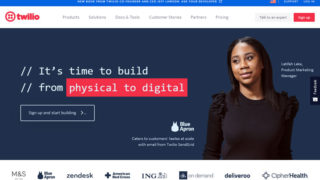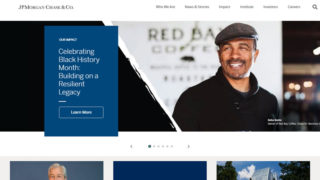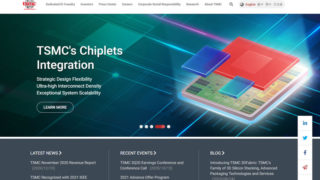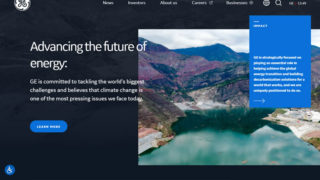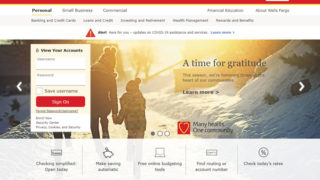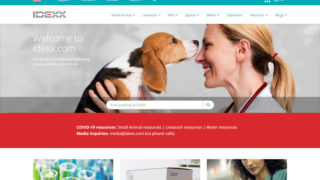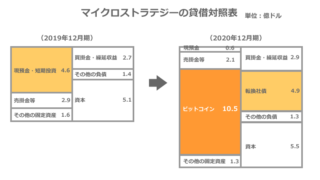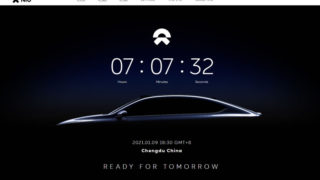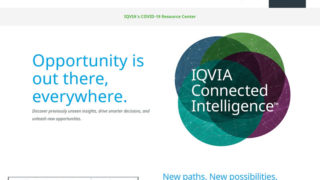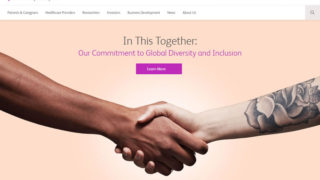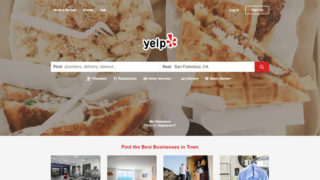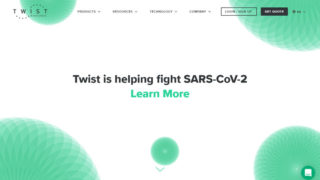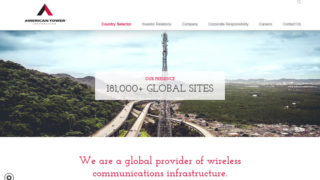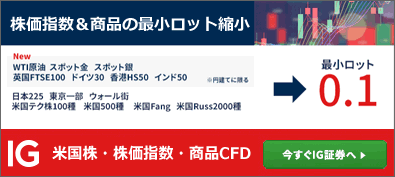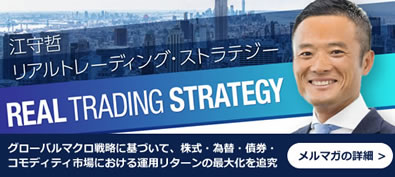個別銘柄の紹介
個別銘柄の紹介米国株をめぐる税金

国内の証券会社を利用して米国株を売買した場合
【配当】
国内証券会社を利用して米国株を売買した場合の配当は;
米国で配当受取り時に源泉徴収され(米国と日本との租税条約により、10%)、その源泉徴収額を差し引いた額に対して、日本国内で再び、国内株式と同様の方法で課税されます(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税を選択できます)。
ただし国内株式と異なり、配当控除の適用はありません。総合課税を選択した場合は、外国税額控除の適用があり、現地国で源泉された税額は一定の範囲内で所得税や住民税から控除することができます。
【譲渡益】
国内証券会社を利用して米国株を売買した場合の譲渡益は;
米国で課税されることはありません。ただし日本国内においては日本株と同様の方法で課税されます(申告分離課税です)。
「金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡」に該当するため、平成25年までのものの税率は、国内株式等と同様に、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率(※)が適用されます(なお平成25年から49年までの25年間は所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされます)。
※軽減税率
2013年1月29日に閣議決定された「平成25年度税制改正大綱」において、上記の10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)は、平成25年12月31日をもって廃止する、と明記されました。
一方で2014年1月から、「NISA」(日本版ISA:少額投資非課税制度)が始まります。NISAとは、非課税口座内で保有する上場株式や投資信託の配当所得や売却益にかかる税金が非課税となる制度です(非課税枠は、年間の累積購入代金100万円までで、非課税となる期間は投資をはじめた年を含めて5年後の12月末までで、非課税投資総額は最大500万円)。
外国上場株式の売却損失がある場合は、「上場株式等の配当等の金額」から控除でき、確定申告を行なうことで最長3年間の繰越控除することが可能です。
(★米国株の売買に、国内証券会社を利用する場合の最大のメリットはこれだと思います。)
海外の証券会社を利用して米国株を売買した場合
以下の前提として、日本の「居住者」(日本国内に住所があるか、又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人)による取引とします。
【配当】
海外証券会社を利用して米国株を取得した場合の配当は;
海外の証券会社を利用して取得した米国の上場株式等の配当を受け取る場合は、「Form W-8BEN」(米国の税務当局である内国歳入庁(IRS)に提出する非居住者証明で、米国の源泉徴収に関する租税条約の恩典を受けるための証明となるもの)を3年に1回提出している場合、日本と米国の租税条約により、10%の軽減税率が適用されます(なお、租税条約が適用されない場合の、米国非居住者に対する源泉税率は30%です)。
(参考)米国と他国間の租税条約に基づく利子・配当等の源泉徴収税率表(米国歳入庁:IRS)
http://www.irs.gov/publications/p515/ar02.html#en_US_2013_publink1000225127
米国で源泉徴収された後の90%部分に対して、(日本居住者は全世界の所得に日本で課税されるので)日本の税金が課されます。この日本で課される税金は、総合課税・申告分離課税を選択します。
米国内で源泉徴収された税額については、外国税額控除の適用があり、一定の範囲内で所得税や住民税から控除することができます。
【譲渡益】
海外証券会社を利用して米国株を売買した場合の譲渡益は;
米国では非居住者に対する譲渡益の課税はありません。日本国内では、「金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡」に該当しないため、10%の軽減税率が適用されず、本則通り、20%(所得税15%、住民税5%)(同様に平成25年からは所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せ)の申告分離課税が適用されます。
国内証券会社を利用した取引と、海外証券会社を利用した取引の損益通算は可能です。
譲渡損失の翌年以後3年間の繰越控除は、国内証券会社を利用した取引のみが対象となり、海外証券会社を利用した取引は適用されません。
★余談ですが、キャピタルゲインに課税しない国や、その国の中で発生した所得(国内源泉所得といいます)だけに課税する国(シンガポール等)の居住者は、税金上とても有利です。