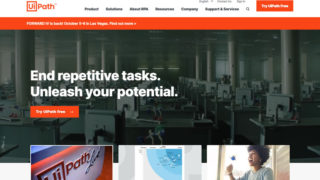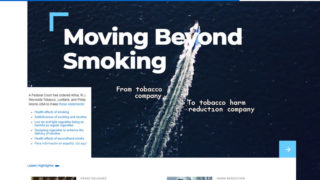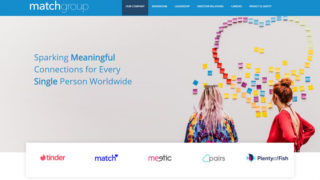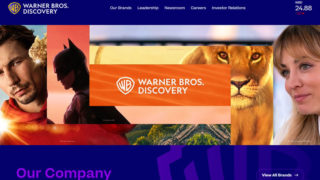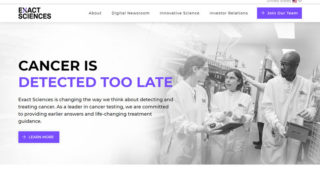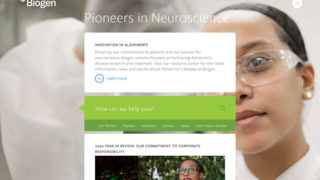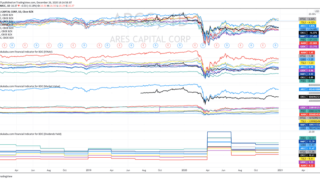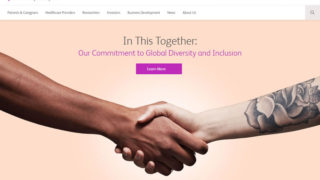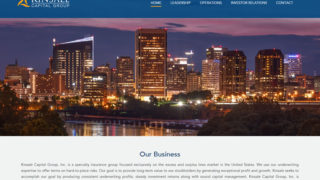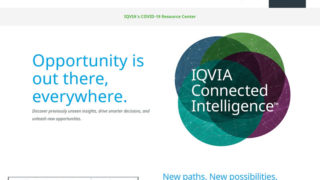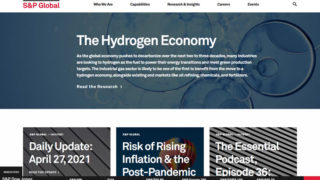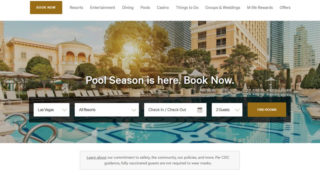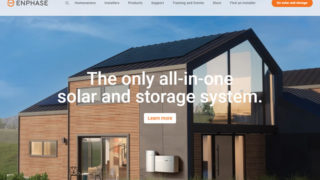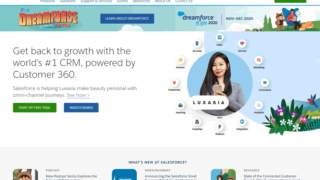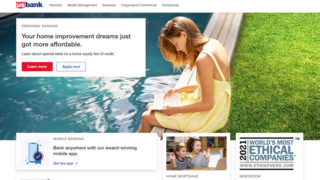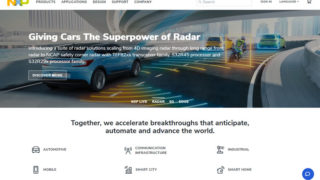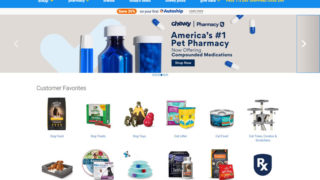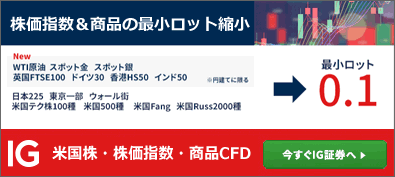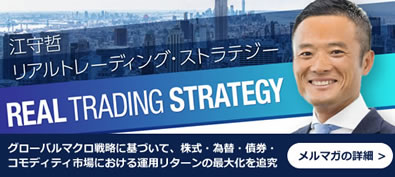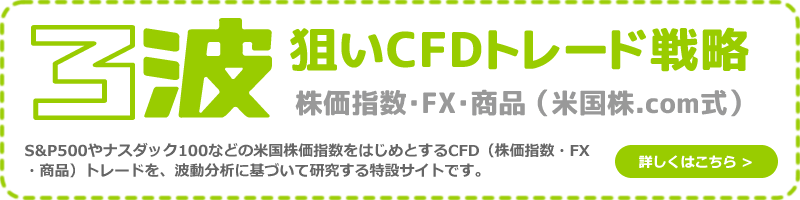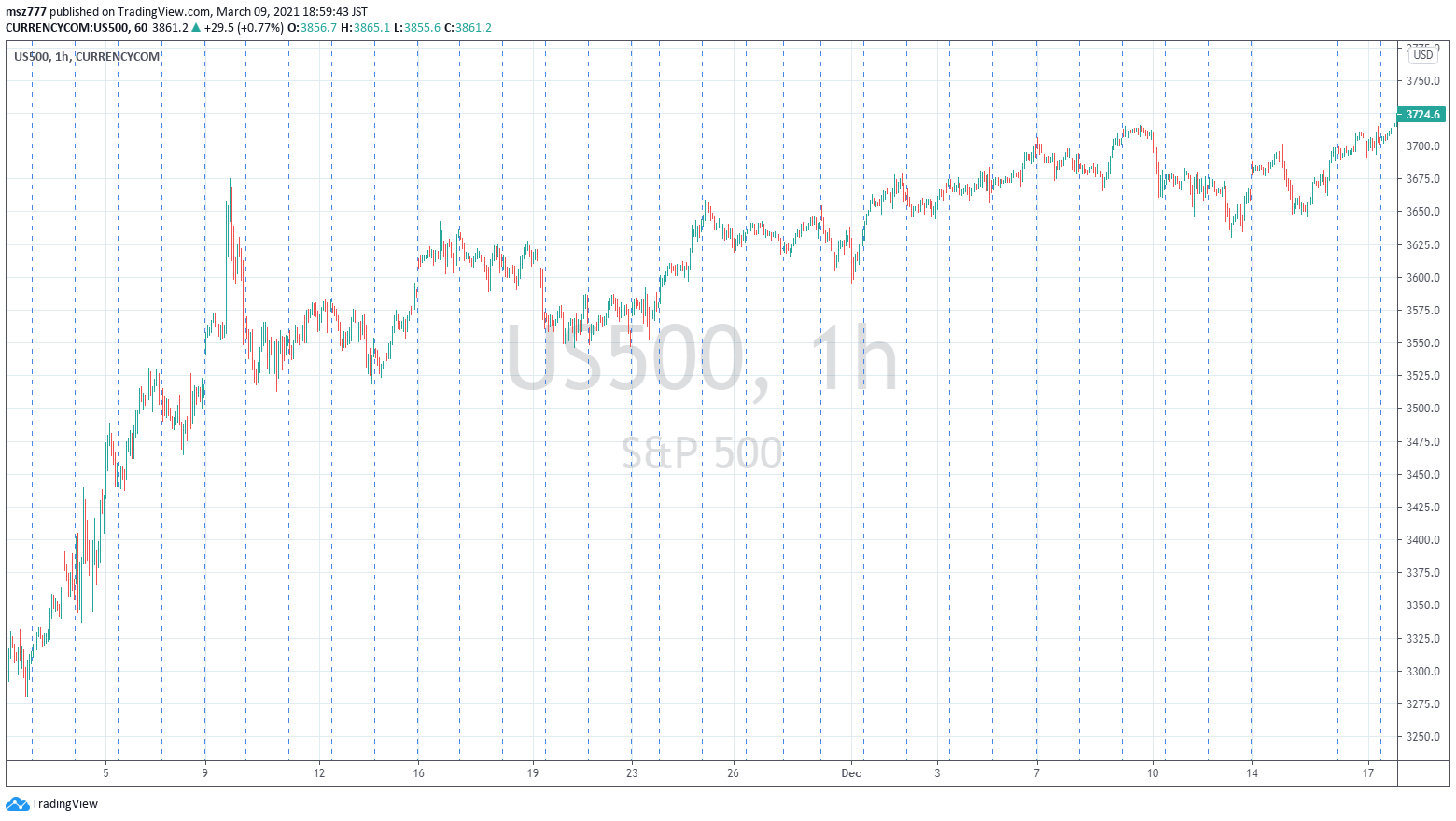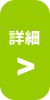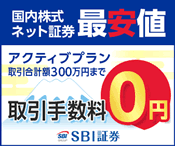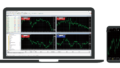特集:株価指数の「自動売買」をMT4ではじめてみよう
(1)はじめのサンプル
(2)参考書籍の紹介
(3)売買ロジックを考えてみよう
(4)自動売買にとって重要なスキル・経験は?
(5)自動売買に最も適した株価指数はどれか?
(6)自動売買のロジックの実例
(7)自動売買EAのバックテストによる評価方法
(8)「バックテスト」よりも「フォワードテスト」が重要
(9)24時間ずっと自動売買するための「VPS」を利用してみよう
(1)はじめのサンプル
(2)参考書籍の紹介
(3)売買ロジックを考えてみよう
(4)自動売買にとって重要なスキル・経験は?
(5)自動売買に最も適した株価指数はどれか?
(6)自動売買のロジックの実例
(7)自動売買EAのバックテストによる評価方法
(8)「バックテスト」よりも「フォワードテスト」が重要
(9)24時間ずっと自動売買するための「VPS」を利用してみよう
はじめに
この特集では、楽天が「株価指数のCFD」の取り扱いを「MT4」で始めたので、これに対応して、「MT4による株価指数の自動売買」の記事を書いています。
今回は、自動売買の売買ロジックについて書いてみたいと思います。
自動売買は「エントリーのロジック」x「エグジットのロジック」
自動売買には;
- 買いまたは売りのエントリーでポジションを持つための、エントリーのロジック
- 上記のポジションを反対売買で決済するための、エグジットのロジック
が必要です。
ここであらためて、実際のチャートを2枚、つづけて眺めてみます。
1枚目のチャートは、昨年の11月~12月の、S&P500株価指数CFDの1時間足です。↓
上昇トレンドの相場ですね。
続いて2枚目は、同じくS&P500株価指数CFDの、今年の1月下旬~3月のチャートです。↓
1月末にゲームストップ株関連で相場が崩れ、その後は長期金利の急上昇によって、膠着相場が続いていますね。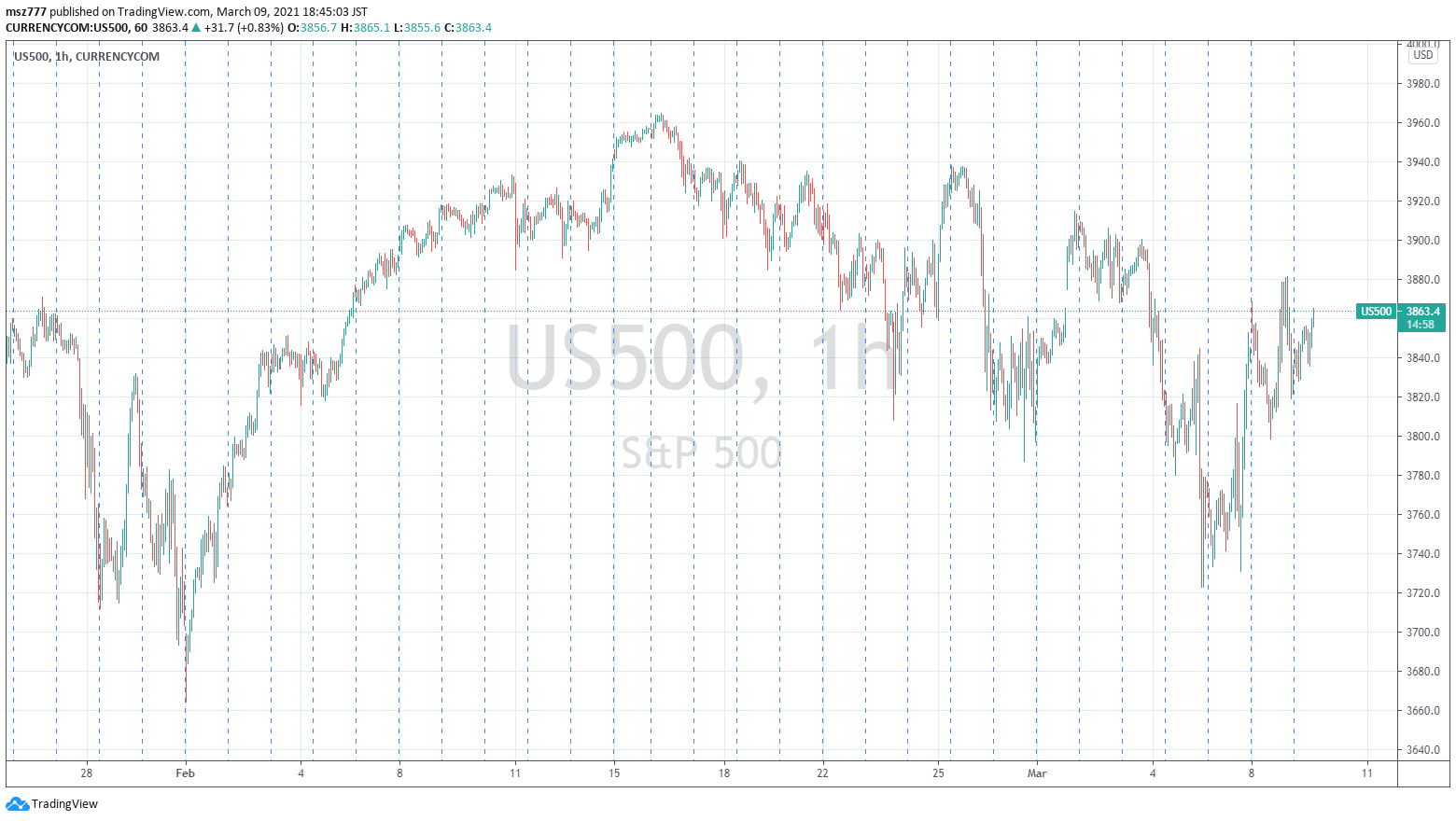
貴方は、上記の2つのチャートで、どのような自動売買ロジックを使いますか?
特に正解はありません。EAの開発者の数だけロジックがあります。以下では、考え方とかヒントを列挙してみたいと思います。
【エントリーロジックの考え方の例】
- 「勝率は低いが、勝つときは大きく勝つロジック」にするか?逆に「勝率は高いが、たまに大きく負けるロジック」にするか?
- エントリーからエグジットまでの時間(デイトレ、スイングトレード、スキャルピング)をどの程度に設定するか?
- エントリーのロジックを、さらに(1)環境認識のためのロジック(条件をフィルタリングするロジック)と、(2)エントリーのタイミングをはかるロジックに分けるのはどうか?
- トレンド相場と、レンジ相場をどのように区分して認識するか?
- トレンド相場と、レンジ相場で別々のロジックにするのはどうか?
- トレンド相場と、レンジ相場で共通して使えるロジックはあるか?
- トレンド相場の「押し目買い」「戻り売り」戦略で、優位性のあるポイントをどのように見つけるか?
- レンジ相場の上限や下限での「逆張り」戦略で、優位性のあるポイントをどのように見つけるか?
- レジスタンスやサポートの「ブレイクアウト」戦略で、優位性のあるポイントをどのように見つけるか?
- ボラティリティが高い相場か、低い相場かを、どのようにして認識すべきか?
- 優位性のある時間帯はあるか?
- エントリーの個数はどうすべきか?1個か複数か?
- 買い・売りの両方か?どちらか一方か?
- 重要な経済指標の発表の前は、EAを止める前提でよいか?
- 流動性が落ちる年末年始などは、EAを止める前提でよいか?
- 最終的なエントリー判断は手動によることにして、その前にある条件がそろったらアラートを出すインジケータとして使う「半自動」の運用はどうか?
【エグジットロジックの考え方の例】
エグジットでも同様に、考え方やヒントを列挙してみたいと思います。
- エグジットのロジックを、エントリーのロジックとは別に設定するか?
- 相場が逆行したときのロスカット(損切り)のロジックはどうすべきか?
- いったん含み益になったあと、逆行してエントリー価格まで戻ったときに「建値決済」をすべきか?
- 固定的な利益確定幅を設定するか?
- (ボラティリティなどの条件を使って)変動的な利益確定幅を設定するか?
- 含み益がのびたらストップを変更していく「トレーリング・ストップ」を使うか?
- ポジションが複数あるときに、どのようにエグジットするか?
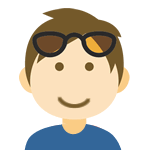
最後まで読んでいただきありがとうございます。
この特集はまだまだ続きます。どうぞよろしくお願いします。